このブログでは本をたくさん紹介しています。
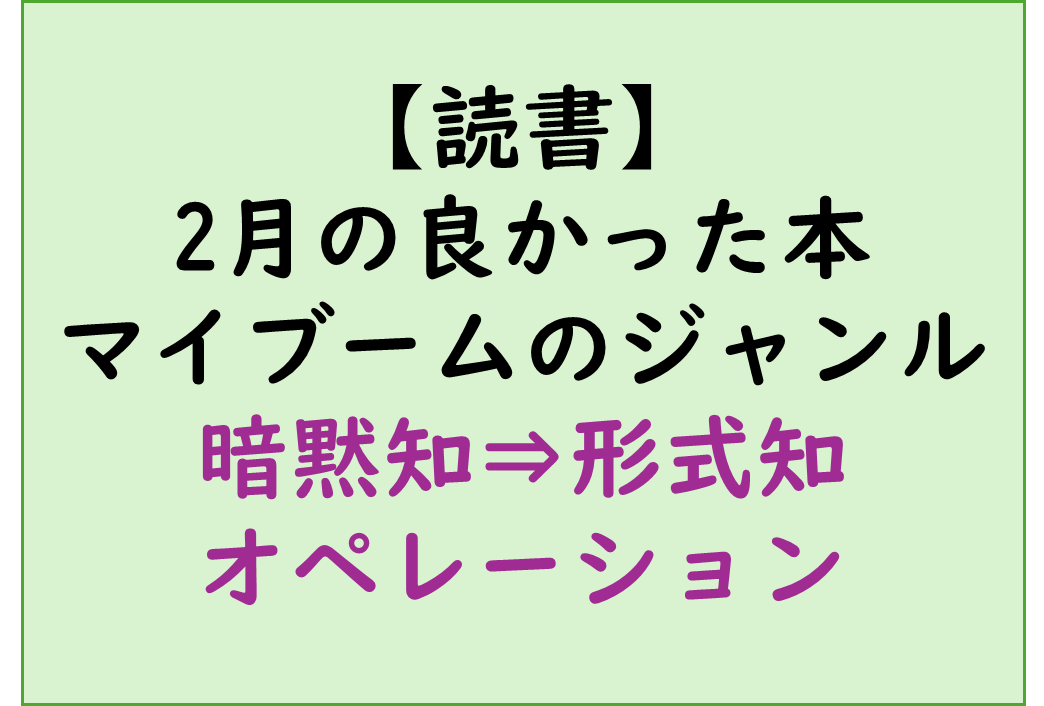
今日は、2月に読んだ本の中から良かった本を紹介します。
1.面白かったオススメ本
ANAのカイゼン
トヨタの工場で使われる「カイゼン」を、非製造業の航空サービス業でどうやって使っているかを書いた本です。フレームワークに当てはめる解説のほかに、空港で60代以上の人が大半を占めていた職種を納得の上でシステム化した事例も書かれていて、とても読みごたえがありました。
リスキリング大全
最近のリスキリング(学びなおし)の全体感を知りたいならこれ1冊と言える本です。ここ数年のリスキリング関係の出版物のトレンドを確実に押さえている本で、内容がとても充実しています。従業員の立場で書かれているのでとっつきやすく読みやすいです。
シン、読解力
この本の読解力は「解釈が1つに決まる文章」を読み解く力のことです。文章を読む時の認知的負荷の解説や、ワーキングメモリにかかる負荷への耐性を付けるトレーニング方法は目を引きました。
二項動態経営
『失敗の本質』を書いた野中郁代次郎氏の本です。アリストテレスや現象学などの難しそうな哲学の思考を、経営に照らし合わせて企業の成功事例/失敗事例を解説しています。暗黙知を形式知にすることは生成AIで実現することはできず、人間にしかできないというSECI(セキ)モデルの解説は目を引きました。
それ、パワハラですよ
上司側を糾弾だけするのではなく、「会社側にはどのような権利があるのか」を解説してくれていることがとてもいいです。ハラスメントを受けた人には「あれはやっぱり許されないことと考えて良かったんだ」と癒しを与えてくれます。また、チームや組織を作る管理職側にとっては、していいことダメなことを整理してくれている便利な1冊です。
後悔しない公務員の転職とリスキリングの技術
公務員が民間企業への転職する時に、とても使える1冊です。アピールポイントを整理することから始まり、民間企業でもすぐに転用できるポータブルスキルのことが分かります。公務員は自治体ごとのルールが関わる特殊な働き方ですが、民間でも活かせるスキルを知ることで、きっと自信につながります。
マッチング理論とマーケットデザイン
面白そうでしたが、難しくて読むのを断念した本です。数学の行列が出てきました。求める人とそれを受ける人のマッチングを自動化する方法を考えている本です。今の時代に沿ったテーマの本だと感じます。
2.私の読書マイブーム
暗黙知から形式知へ
最近の面白い本は「生成AIの技術が高まる環境で、人間はどのように働けるか」をテーマにしています。生成AIがタッチしない暗黙知から形式知(=明文化された情報)への情報変換を人間がどのように行えばいいかを書いている本に、立て続けに2-3冊出会いました。
「暗黙知」から「形式知へ」は、私の中で数年間は続く大きなテーマになりそうです。
オペレーション
これは業務フローを定型化する話に通じます。
人口減少で働き手が減る時代では、オペレーションの仕組みづくりをする人の価値が高まると推測しています。私がベトナムに旅行に行った時は、海外旅行という場面で目の前の知らないベトナム人は信用ならないと警戒する気持ちが強くありましたが、紙幣を通じた取引やカフェの座席の案内といったオペレーションはある程度信用することができました。
最近は、日本で仕事や生活をする時に、オペレーションが整っているなら、国籍や年齢に関わらず相手への信用度は高められるという思いが強まっています。「何でもない人」を組織の一員にする流れのシステム化は、これまでに大企業が長い年月をかけて整備してきたことです。
これからは、企業の規模に関わらず、部署の数人のチームメンバーが数週・数か月のスパンで成果を求められる時代だと考えています。これまで取り組んだことのない新しい目標に対して、業務フロー作成や役割分担をしていく機会はどんどんと増えていくと想像しています。仕組みづくりの実践法をテーマに本を読み進めていくことで、近い将来にのニーズに備えられると考えています。